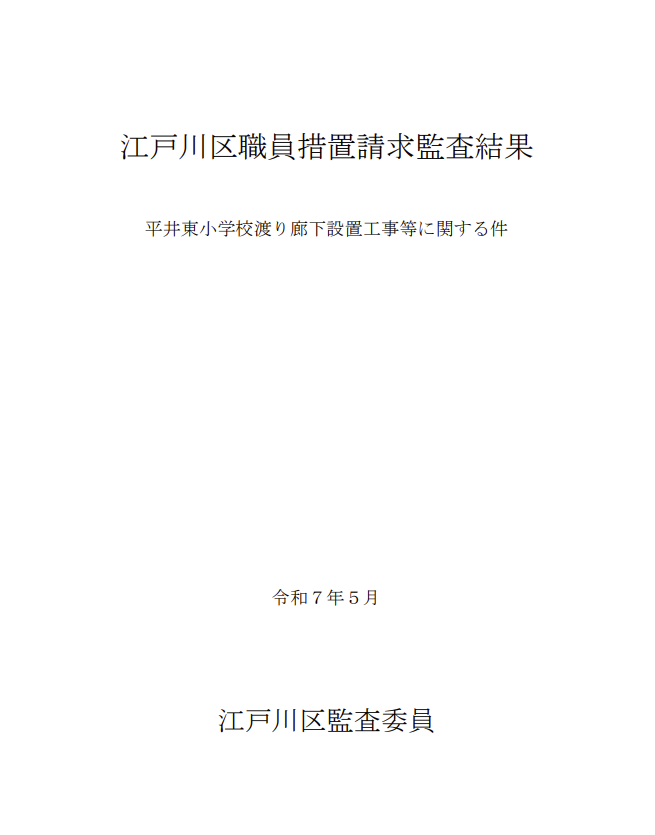本日、文教委員会に出席してまいりました。今回の委員会では、多岐にわたる重要な議題が審議されましたので、その内容をレポートとしてまとめたいと思います。
平井東小学校渡り廊下の屋根等の撤去について
委員会冒頭では、今定例会に提出されている議案審査が行われました。その後、まず執行部から報告されたのが、区立平井東小学校の校舎とすくすくスクールの建物との間に設置されていた渡り廊下の屋根と柱部分が、令和7年3月1日に撤去された件です。
撤去の理由は、建築基準法に定める必要な手続きが取られていなかったこと、そして区の調査により安全性が確認できなかったためと説明がありました。特に、柱のアンカーボルトの形状や長さが不足していたことが指摘されたようです。
児童の安全確保を最優先に考え、学校休業日に緊急工事として対応したとのことですが、設置時の経緯については引き続き調査が進められるとのことです。11月の文教委員会でも指摘があったにも関わらず、対応が遅れたのではないかという指摘も他会派議員から出ており、今後の調査結果が注目されます。
また、平井東小学校だけでなく、他の二つの小学校にも仮設廊下が設置されていることから、これらの安全性についても検証を進めるべき、という意見が同じ議員から指摘されていました。
不適切契約事案の検証及び再発防止対策検討委員会の設置について
次に、大きな議題として取り上げられたのが、一般競争入札を避け随意契約を行うために分割して発注していた請負工事などの不適切な契約事案についてです。この事案の検証と再発防止策を検討するため、弁護士や学識経験者、建築専門家からなる第三者委員会が設置され、同日の午後3時から初回の検討委員会が開催されるとの報告がありました。もちろん、私もこの第三者委員会には傍聴の申し込みをしており、参加してきましたので別途ブログにまとめる予定です。
委員会の名称は「江戸川区不適切契約事案の検証及び再発防止対策検討委員会」であり、構成委員は5名(今井学氏(弁護士)、上野武氏(建築専門家)、楠茂樹氏(学識経験者)、中里浩氏(学識経験者)、野村裕氏(弁護士))であることが報告されました。
所掌事項として、不適切契約事案並びに原因究明及び再発防止のために確認が必要とされた事案の検証、原因究明及び再発防止対策の検討などが挙げられています。
本日の文教委員会では、見積書の内容確認状況や類似建築物との比較検討の有無など、詳細な質疑応答が行われました。後述しますが、不正競争防止法や私文書偽造の疑いといった厳しい指摘も他会派議員から出ており、教育長や関係部署の責任が問われる場面もありました。
第三者委員会での検証だけでなく、教育委員会や用地経理課も合わせて検証を進めていく必要性が強調されていました。
見積書の筆跡問題に焦点
今回の不適切契約事案に関する議会質疑において、提出された見積書の筆跡に関する重大な疑惑が浮上しました。
議員からの指摘によりますと、情報開示請求によって入手した資料の中に、分割された工事に関する3社分の見積書が含まれており、その多くが手書きで作成されているとのことです。
問題視されたのは、この3社すべての見積もりが、まるで同一人物によって書かれたかのように見える点です。 議員はこれに対し、不正競争防止法や私文書偽造に該当する可能性を強く示唆し、「大変なことですよ」「詐欺だ」といった厳しい言葉で、事態の重大性を訴えました。 各社が自社のものとして押印しているにもかかわらず、筆跡が酷似している状況に、強い懸念を示しています。
教育推進課長(副参事兼務)は、この指摘に対し、見積書の筆跡が類似している点については事案が発覚した9月か10月ころには把握していたと答弁していました。
議員からは「もうその時点で告発してくださいよ」という強い要求が出されました。 またこれは単なる手続き上の問題ではなく、区民の財産が侵害されているという認識を示すべきだと主張されていました。
また、問題に気づいてから半年もの間、第三者委員会に結論を委ね、その間、事実を公表しない区の姿勢を強く批判しました。 そして、問題の早期解明と透明性の確保、情報公開を強く求めています。
この見積書の筆跡に関する疑惑は、今回の不適切契約事案が単なる手続きの不備に留まらない、より根深い問題を抱えている可能性を示唆しているのではないでしょうか。 第三者委員会による徹底的な検証はもちろん大事なことですが、議会側からもより迅速かつ積極的な対応を求める必要があると、私から改めて意見を述べてきました。
第四次江戸川区 学校教育情報化推進計画(案)について
委員会では、令和7年度~令和11年度の5年間を計画期間とする「第四次江戸川区 学校教育情報化推進計画(案)」についても報告が行われました。
この計画は、「誰ひとり取り残さず、江戸川の子どもたちの資質・能力を育む」を基本目標に掲げ、ICTを活用した教育の推進、教員のICT活用指導力の向上、ICT環境の整備、ICT推進体制の整備と校務の改善という4つの基本方針に基づき策定されています。
計画案では、現状分析や課題認識を踏まえ、各基本方針における具体的な推進目標と施策が詳細に示されています。例えば、児童生徒のICT活用頻度や情報モラルの学習状況、教員のICT活用指導力、校内ネットワーク環境の整備、非常時におけるICT活用体制、校務の効率化などが具体的な目標値とともに示されていました。
特に、GIGAスクール構想の推進や「令和の日本型学校教育」の実現に向け、ICTを効果的に活用し、個別最適な学びと協同的な学びを推進していく方向性が明確に示されています。また、教員の働き方改革の推進においても、ICTの活用が重要な役割を果たすことが期待されています。
計画案については、令和7年3月1日(土)~3月31日(月)の期間で、郵送、窓口、インターネットによる意見募集が行われることが報告されました。
意見募集はこちらで行われています。ぜひご覧の皆様からも、コメントを送っていただきたいと思います。
その他
委員会では、その他にも以下の報告事項がありました。
- 令和7年度 地域学習塾「EDO塾」実施報告: 成績中・上位で学ぶ意欲が高い中学校3年生を対象とした地域学習塾「EDO塾」の成果として、2学期の通知表における成績上昇や、入塾テストと外部模試(Vもぎ)の比較における偏差値の平均+5.76ポイントの上昇、高校入試結果(速報)などが報告されました。希望校への進学率は86.0%という高い実績を上げています。
- 学校サポート教室の名称変更について: 不登校及び不登校傾向の児童・生徒の居場所・学び場である学校サポート教室の名称を、アンケート結果を踏まえ「みらいサポート教室」に変更することが報告されました。教室に通う児童・生徒の声も紹介され、「こころが明るい未来に向かう場所」「自分たちの未来を支えてくれる場所」といったポジティブな意見が多く寄せられていることが紹介されました。
まとめ
今回の文教委員会では、平井東小学校の渡り廊下撤去問題や不適切契約事案に関する厳しい質疑応答が行われる一方で、学校教育情報化推進計画案や児童生徒の素晴らしい活躍の報告など、多岐にわたる議題が審議されました。特に、不適切契約事案については、今後の第三者委員会の検証結果を注視していく必要があると感じました。
また、教育の情報化や学びの多様化に向けた取り組みも着実に進められていることが確認できました。意見募集が行われる「第四次江戸川区 学校教育情報化推進計画(案)」についても、区民一人ひとりが関心を持ち、意見を発信していくことが重要だと感じました。
傍聴を通して、区の教育行政に対する理解を深める良い機会となりました。今後も、文教委員会の動向を注視し、皆様に情報をお届けしていきたいと思います。